TNFD提言に基づく開示
生物多様性に関する考え方
マルハニチログループは、世界の海洋から漁獲・養殖される水産物を中心とした自然の恵みを生業として140余年にわたり事業を継続してきました。マルハニチログループの事業は他にも農・畜産資源、水や土壌、昆虫等による花粉媒介などのさまざまな自然の恵み、つまり生態系サービスに大きく依存していますが、経済活動に伴う森林伐採や工業化、環境汚染などにより生物多様性の劣化が近年急速に進んでおり、これらを重要な社会課題であると認識しています。 生物多様性COP15にて採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」のミッションである、自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性の損失を止め、反転させるための行動「ネイチャーポジティブ」に貢献することを目指し、マルハニチログループは、原材料調達から製品廃棄に至るバリューチェーン全体での事業活動において、生物多様性への依存と影響ならびにリスクと機会を把握し、その保全・再生に向けた取組みを推進します。
TNFDへの賛同表明(情報開示方針)
マルハニチログループは自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)のアダプターとして登録しており、2023年9月に公開された、TNFDから最終提言(v1.0)に沿った開示推奨項目を参照し情報開示に努めています。
ガバナンス
マルハニチログループのサステナビリティ推進体制
気候変動、自然関連課題への対応は、常務執行役員を委員長として、マルハニチロ(株)取締役を兼務する役付執行役員、関連部署担当役員、関連部署長を委員、社外取締役、監査役(オブザーバー)から構成されるサステナビリティ推進委員会を中心に推進しています。サステナビリティ推進委員会は、マルハニチログループサステナビリティ戦略全般の企画立案や目標設定、およびグループ各社の活動評価をしています。サステナビリティ推進委員会は四半期ごとに年4回開催されており、マテリアリティ“生物多様性と生態系の保全”を含む各マテリアリティの進捗を各責任者およびプロジェクトリーダーが報告し、積極的な討議を行っています。サステナビリティ推進委員会で討議された内容は、少なくとも年4回、経営会議を通じて取締役会へ報告・答申します。
自然関連課題への取り組みで重視される先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他ステークホルダーなど当社グループの事業に関わるあらゆる人々に対して、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」など国際標準に準拠して策定した「マルハニチログループ人権方針」において人権尊重を掲げています。加えて、従業員に対して人権研修を実施し、各々の事業活動で発生しうる人権侵害リスクについて、生物資本消費に伴う消費者・地域住民に対する人権侵害も含めて抽出し、その結果を深刻度と発生可能性を人権リスクマップとして、マトリックスでまとめています。これらの人権課題はその対応策も含めてサステナビリティ推進委員会で進捗状況を報告・討議し経営会議を通じて取締役会へ報告・答申しています。
マルハニチロ(株)ではサステナビリティ経営の推進を目的とし、経営陣・社内取締役の報酬についてESG指標を評価指数に組み込んだ中期業績連動型株式報酬を導入しています。2025年に公表した中期経営計画 「For the ocean, for life 2027」(2025 年度~ 2027 年度)では“生物多様性と生態系の保全”、“事業活動における人権の尊重”を含むマテリアリティ毎に2027年度目標または2030年度目標(KPI)を設定し進捗管理を行っており、これらの進捗は従業員の人事評価にもつながっています。
参考リンク
自然資本に関連するイニシアチブへの参画

マルハニチログループは、水産物をコアにグローバルなバリューチェーンを通じてビジネスを展開しています。特にその調達活動と水産資源は密接に関係しており、幅広いバリューチェーン上には単一企業、民間セクターのみでは解決できないサステナビリティ課題が多く存在していることが懸念されます。包括的な取組み推進のためには、同業他社や行政、科学者、NPO/NGOとの協働が不可欠であると考えており、マルハニチログループは、国内外のさまざまなイニシアチブへ自主的に参画し、サステナビリティ推進委員会および経営会議で進捗を報告しています。
参画している生物多様性に関連するイニシアチブ
- 国連グローバル・コンパクト
- 持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)
- クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)
- 日本経団連生物多様性宣言
- 生物多様性のための 30by30 アライアンス
- ジャパンブルーエコノミー推進研究会
Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)に参画への参画

SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship)は、世界水産大手企業6社と、海洋・漁業・持続可能性を研究する科学者が、持続可能な水産物の生産と健全な海洋環境を確保するために、科学的根拠にもとづく戦略と活動を協力しながら主導することを目的に2016年に設立されたグローバルなイニシアチブです。
SeaBOSの活動は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)、特に「目標14 海の豊かさを守ろう」に積極的に貢献するとしています。
現在は下記5つのタスクフォースに分け、解決に向けた議論を行っています。

マルハニチロはSeaBOSの立ち上げから参加し、2018年9月、組織設立と同時に当社社長(当時)の伊藤滋が初代会長に指名され、2020年10月まで会長として従事しました。現在はタスクフォースVの共同リーダー、タスクフォースⅠ、ⅢおよびⅥのメンバーとして活動しています。
参考リンク
SeaBOSの取組み
生物多様性に関連するステークホルダーエンゲージメント

マルハニチログループが取扱う水産物には、多くのリスク・機会があります。健康価値の高い貴重なたんぱく源として持続的に社会に提供していくためには、可能な限りリスクを排除し、機会を最大化することが必要であるという認識のもと、それらについての専門的な知識・広い見識を持つ社外有識者(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン、一般社団法人エシカル協会)との意見交換を行いました。
特集 次の100年に向けて、水産物を持続的に提供するためのマルハニチログループの使命戦略
マテリアリティ
マルハニチログループはステークホルダーの関心(社会視点から見た重要性)とマルハニチロへの影響(自社から見た重要性)の2方向から課題を検討し、サステナビリティ分野における重点課題(マテリアリティ)を9つ特定しています。そのうち自然資本、生物多様性に関連するマテリアリティとして「気候変動問題への対応」と「生物多様性と生態系の保全」を特定しています。
参考リンク
重点課題(マテリアリティ)の特定・見直し
全事業ユニットのバリューチェーンに関連する生物多様性の依存・影響度の分析と分析対象の決定
マテリアリティの1つである「生物多様性と生態系の保全」では、KGI(2030年のありたい姿)を“取扱水産資源について、資源枯渇リスクがないことを確認している”としています。この実現のために、設定しているKPIの一つ“生物多様性リスク評価実施”に関連して、当社事業の生物多様性への依存・影響度の分析を、TNFDが提唱するガイダンスであるLEAPアプローチに従って実施しました。当社グループのバリューチェーンは複雑かつ多岐にわたっているため、全事業ユニット(2023年当時)毎のバリューチェーンに関連する生物多様性因子を確認し、各因子への依存・影響度を分析後、より詳細に分析を進める対象の絞り込みを行いました。対象の絞り込みは下記4段階に分けて実施しました。

STEP1~3 対象ユニットの決定
事業と自然資本との関わりを可視化するために、ENCORE※1による全事業ユニットのバリューチェーンの上流~下流の自然資本への依存・影響度の一次評価を実施し、その後当社グループの事業実態に合わせた依存度・影響度の二次評価を実施しました。得られた依存度・影響度の二次評価結果から、各ユニットの依存度・影響度のスコアを算出※2し、各ユニットのスコアを依存度・影響度マッピング図にプロットした結果、下図の通りとなったため、分析評価対象ユニットを海外ユニット・養殖ユニットに決定しました。
- ※1 自然資本資産と環境変化の要因に関する地理空間データセット、および生態系サービスを生産プロセスに結びつける定性的影響/依存度評価ツール
- ※2 ENCOREによるNA / VL /L / M / H / VHの6段階での評価を対応する数値(0-5ポイント)に変換し、バリューチェーン上での各評価の項目数と直接操業内外を考慮し、各ユニットのバリューチェーン全体での依存度・影響度のスコアを算出
参考データ
- 漁業ユニットバリューチェーン上の自然資本への依存・影響度(二次評価後)
- 養殖ユニットバリューチェーン上の自然資本への依存・影響度(二次評価後)
- 海外ユニットバリューチェーン上の自然資本への依存・影響度(二次評価後)
- 全ユニット別バリューチェーン上の自然資本への依存・影響度(二次評価後)

STEP4 対象魚種の決定
ユニット単位では取り扱う魚種などが多いため、以降の分析を詳細に行うために対象魚種の選定を行いました。対象魚種は経営上の重要性を考慮し決定し、海外ユニットにおいては当社グループの天然魚で38%の取り扱いを占め※、自社グループでの生産・加工を行っているスケソウダラを対象としました。養殖ユニットにおいては海面養殖の主要魚種である、マグロ、ブリ、カンパチを対象としました。
※2022年度実施の第2回マルハニチログループ水産資源調査結果に基づく


図 第2回マルハニチログループ水産資源調査結果に基づく魚種別取扱量
表 対象魚種の選定理由と関連する拠点地域
| 事業ユニット | 関連する事業プロセス | 対象魚種 | 選定理由 | 対象拠点/地域 |
|---|---|---|---|---|
| 海外ユニット | 漁業 |
|
|
|
| 養殖ユニット | 養殖 |
|
|
|
影響を受けやすい地域の分析(Locate)
対象魚種それぞれの漁獲・養殖地域が、TNFDガイダンスで影響を受けやすい地域(Sensitive Locations)および重要な地域(Material Locations)と定義される、「優先地域」に該当するか分析しました。
マルハニチログループが取り扱うスケソウダラの主要漁獲地域である、米ベーリング海およびカムチャッカ半島西側を分析した結果、想定されるスケソウダラの漁獲海域の一部または大部分が、生態的及び生物学的に重要な海域(EBSAs)や保護海域内、もしくはその周辺海域である可能性を識別しました。以上によりマルハニチログループが取り扱うスケソウダラの主要漁獲地域は、すべて「優先地域」として特定しました。
マルハニチログループの国内養殖場13拠点を分析した結果、拠点から1km範囲の海域について、大分県佐伯市と鹿児島県鹿児島市の養殖場を除く11拠点の養殖場が、生物多様性の観点から重要性の高い海域(環境省)に該当することが確認されました。また13拠点すべての養殖場が、protected planet®における、Marine Protected area (MPA)に含まれることを確認しました。以上により養殖場13拠点は、すべて「優先地域」として特定しました。


図 対象魚種それぞれの漁獲・養殖地域
漁業(スケソウダラ)、養殖(ブリ・カンパチ・マグロ)の依存・影響の分析(Evaluate)
次に関連する依存と影響の関係の精緻化を行うため、スコーピングの際にENCOREを用いて調査した依存・影響の情報に加えて、論文・レポート等の調査を行いました。その結果、以下の表の通り当社事業のリスク・機会に繋がり得る重要な依存と影響があることを認識しました。
表 スケソウダラ漁業における依存と影響に関する重要因子
| 依存影響 | 因子 | (参考)ENCOREの評価による影響の大きさ | 重要因子と判断した理由 | |
|---|---|---|---|---|
| スケソウダラ漁業 | 影響 | 海洋生態系の生息環境 | Very High | ENCOREでの評価の通り、漁業は操業の規模、漁具、漁法などにより、海洋生態系の生息環境に重要 な負の影響を与える可能性があるため。 |
| 天然魚の資源量 | High | ENCOREでの評価の通り、乱獲及び混獲は、天然魚の資源状態や海洋の生態系へ重要な影響を与える 可能性があるため。 | ||
| 漁業従事者の人権 | - | ENCOREでは評価されていないが、IUU漁業などはサプライチェーン上の人権侵害への影響につなが る可能性があるため。 | ||
| 依存 | 産卵・生育・生息地 | Very High | ENCOREでの評価の通り、産卵・生育・生息地は、特定の種の個体の繁殖に非常に強い関係を持っており、スケソウダラの資源量はこれらに大きく依存しているため。 | |
| 水質 | Very High | ENCOREでの評価の通り、海水の化学的状態を保持する生態系サービスは海洋生物の産卵・生育・生 息に大きな影響を与えており、スケソウダラの資源量はこれらに大きく依存しているため。 |
表 養殖における依存と影響に関する重要因子
| 依存 影響 |
因子 | (参考)ENCOREの評価による影響の大きさ | 重要因子と判断した理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 養殖 | 影響 | 海底土壌・海水水質 | High | ENCOREでの評価の通り、直接的に海洋生態系に接する海面養殖においては抗生物質や流出プラスチック等による海底土壌・海水水質の汚染や、養殖魚の生息によるBOD(生物化学的酸素要求量) の上昇は、注意すべき影響と考えられるため。 |
| 海洋生態系 | High | ENCOREでの評価の通り、養殖魚の餌は天然魚が主であり、漁業は操業の規模、漁具、漁法などにより、海洋生態系の生息環境に重要な負の影響を与える可能性があるため。 | ||
| 他の養殖魚 | High | ENCOREでは評価されていないが、養殖魚間の疾病の蔓延等により、他の養殖魚への影響を与える可 能性があるため。 | ||
| 依存 | 生物由来原料 | Very High | ENCOREでの評価の通り、養殖魚の餌は天然魚等の生物由来原料が不可欠であるから。 | |
| 水質(海水) | Very High | ENCOREでの評価の通り、赤潮の発生やBOD(生物化学的酸素要求量)の上昇等の海水水質の悪化は、養殖の生産性に大きく影響するため。 | ||
| 水流(海水) | Very High | ENCOREでの評価の通り、海水水質は養殖の生産性に大きく影響を与え、海水水質は海水水流に大きく影響されるため。 | ||
| 洪水 | High | ENCOREでの評価の通り、洪水・暴風雨は急激な養殖環境の変化を引き起こす可能性があるため。 | ||
| 大気・地盤 | High | ENCOREでの評価の通り、大気・地盤はの急激な変化(洪水・暴風雨等)は養殖環境の急激な変化を引き起こす可能性があり、また気候変動は海水温上昇を引き起こすことが危惧され、養殖の適地を変化させる可能性があるため。 |
評価(Assess)方法
重要な依存と影響の因子に関して、2種類のシナリオにて物理・移行リスクの特定、および3種類のシナリオにて、機会の特定を実施しました。特定したリスク・機会に対して、表に示すTNFDが提示している優先順位付けの判断基準に沿って5段階で強度(財務影響度)を評価しました。発生可能性についてはCOSO (トレッドウェイ委員会支援組織委員会)の委託によって作成された一般的なリスクアセスメント手順(Risk Management in Practice)を参考に、表の発生可能性の評価基準に記載の「頻度」か「可能性」どちらかの基準を用いて評価しました。その後、強度と発生可能性の値を表の財務インパクト判断基準に当てはめ、財務インパクトを3段階で評価しました。
表 リスクの財務影響度評価基準
| 財務影響 | 法規制違反・訴訟 | |
|---|---|---|
| 適用される TNFDのリスク分類 |
全て特に物理リスク移行リスクー政策、技術、市場(うち消費者関連) | 移行リスクー責任/負債 |
| 5 | 【定量】経常利益への影響が20%以上 【定性】
|
|
| 4 | 【定量】経常利益への影響が10%以上 【定性】
|
|
| 3 | 【定量】経常利益への影響が1%以上,10%未満 【定性】
|
|
| 2 | 【定量】経常利益への影響が1%未満 【定性】
|
|
| 1 | 【定量】具体的な財務影響はほぼ生じない 【定性】
|
|
表 機会の財務影響度評価基準
| 財務影響 | 法規制違反・訴訟 | |
|---|---|---|
| 適用されるTNFDのリスク分類 | 資源効率改善、製品とサービス市場、資本フロー&資金調達 自然資源の持続可能な利用、生態系の保護、回復、再生 | 評判 資本フロー&資金調達 |
| 5 |
|
|
| 4 |
|
|
| 3 |
|
|
| 2 |
|
|
| 1 |
|
|
表 発生可能性の評価基準
| 判断基準 | ||
|---|---|---|
| スケール | 頻度 | 可能性 |
| 5 | 1年に複数回 | ほぼ確実 |
| 4 | 1年に1回程度 | (可能性は明らかに)高い |
| 3 | 1~3年に1回 | (発生する可能性の方が高い)中程度 |
| 2 | 3~5年に1回 | (高くはないが)可能性がある |
| 1 | 5~10年に1回 | (可能性は明らかに)低い |
表 財務インパクト判断基準

評価分析に使用するシナリオ
シナリオの選定と分析はTNFD フレームワークが推奨する、自然と生態系の劣化の程度と、サステナブル市場(サステナブルな商品を好む市場)の反応の2 軸による4象限(#1~#4)を想定し、採用するシナリオを検討しました。

スケソウダラ漁業における採用シナリオとリスク分析結果
スケソウダラ漁業は、既に厳格な資源管理下にあり、自然と生態系の劣化度が小さいシナリオも十分想定できたため、シナリオ#1(自然や生態系の劣化が軽微で消費者がサステナブルな商品を好む)とシナリオ#3(自然や生態系の劣化が深刻で、消費者がサステナブルな商品が市場に浸透しない)を採用しました。
シナリオ#3 を想定した場合、特に 3 つの移行リスクについて財務インパクトが High になると評価しました。スケソウダラは厳しく資源管理されている資源であるものの、今後海水温の上昇等の外部的な影響で資源量および漁獲量が著しく減少した場合、漁業規制の強化などの移行リスクは高まると考えられました。
表 スケソウダラ漁業シナリオリスク分析結果
| 依存・影響 | 重要因子 | 物理リスク: 自然災害などの物理的要因によって 引き起こされるリスク 移行リスク: 企業が環境への適応と持続可能性への 移行を試みる際に発生するリスク |
シナリオ#1

|
シナリオ#3

|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リスクの 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | リスクの 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | |||||
| スケソウダラ漁業 | 影響 | 海洋生態系の生息環境 | 移行リスク | 政策 | 1 | 1 | Low | 乱獲は強く規制されており、環境影響も天然水産物に影響を与えるほどではない。資源量および漁獲量は維持される。 | 4 | 3 | High | 海水温の上昇など外部的な影響で、資源量および漁獲量は著しく減少する。 |
| 天然魚の資源量 | 市場/評判 | 1 | 2 | Low | シナリオの設定により、天然水産物の資源量は変わらず、漁獲量は維持される。一方で海水温の上昇などによる生息地環境の変化は顕在化しており、漁獲量への影響は否定できない。 | 4 | 5 | High | 海水温上昇等の生息地環境の変化によりスケソウダラの資源量は著しく減少しており、事業収益は大きく悪化する。 | |||
| 漁業従事者の人権 | 賠償責任 | 3 | 3 | Medium | 水産資源量は変化しない が、より強い生態系保護の観点から漁獲割当量や漁業エリアの制限が厳しくなり、収益性が一定程度低下 する可能性がある。 | 4 | 4 | High | 水産資源量の著しい減少を背景にスケソウダラの漁獲制限や禁漁等の強い規制が起こる可能性がある。 | |||
| 依存 | 産卵・生育・生息地 | 物理リスク | 急性 | 1 | 3 | Low | 消費者はより持続可能な商品を選好するようになり、市場ニーズに応えるため認証の拡大等追加コストが発生するが収益性への負の影響は軽微 | 2 | 4 | Medium | 資源量の減少による価格への影響はあるものの、安価な魚種であるため、2030年頃 を想定すると、コスト重視のマーケットから敬遠されるほどの価格にならない想定であり、収益悪化の程度は限定的 | |
| 水質 | 慢性 | 2 | 1 | Low | マルハニチロおよび調達企業の法令遵守は徹底されており、コンプライアンス違反が発生する可能性は極めて低い | 2 | 1 | Low | マルハニチロおよび調達企業の法令遵守は徹底されており、コンプライアンス違反が発生する可能性は極めて低い (ただし、市場にはIUU漁業による製品が横行し、トレーサビリティのない調達品に IUU産品が含まれる可能性がある) | |||
養殖の採用シナリオとリスク分析結果
養殖は、飼料における天然魚への依存が大きく、飼料に関わる天然魚の漁獲は減少傾向にあるため、シナリオ#2(自然や生態系の劣化が顕著で、消費者がサステナブルな商品を好む)とシナリオ#3(自然や生態系の劣化が顕著で、消費者がサステナブルな商品が市場に浸透しない)を採用しました。 どちらのシナリオにおいても 3 つの物理リスクについて財務インパクトが High になると評価しました。慢性リスクとして、海洋の天然資源量の減少に伴う天然由来の飼料の調達コスト上昇、もしくは、代替飼料の開発・調達コスト上昇による収益性の悪化が想定されました。また急性リスクとして、養殖場の環境変化に伴う養殖魚の生育悪化による収益性の減少、気象災害による施設等へのダメージ回復へのコスト上昇が想定されました。
表 養殖シナリオリスク分析結果
| 依存・影響 | 重要因子 | 物理リスク: 自然災害などの物理的要因によって 引き起こされるリスク 移行リスク: 企業が環境への適応と持続可能性への 移行を試みる際に発生するリスク |
シナリオ#2

|
シナリオ#3
 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リスクの 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | リスクの 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | |||||
| 養殖 | 影響 | 海底土壌・海水水質 | 移行リスク | 政策 | 2 | 2 | Low | 沿岸生態系保護のために規制が強化され、養殖場は移動を余儀なくされるため、一時的な設備投資および運営コストの増加が発生する。一方で市場は環境保全のための価格転嫁を受け入れるため、収益性への影響は一過的 | 2 | 3 | Medium | 沿岸生態系保護のために規制が強化され、養殖場は移動を余儀なくされるため、一時的な設備投資および運営コストの増加が発生し、収益性が悪化する |
| 海洋生態系 | ||||||||||||
| 評判 | 2 | 2 | Low | 消費者はより持続可能な商品を選好するため、より環境負荷の低い代替たんぱく質需要に合わせたより強力な対策が必要となる。 | 3 | 3 | Medium | サステナブルな高価格商品の市場 シェアが減少し、売り上げが低下する。 | ||||
| 他の養殖魚 | ||||||||||||
| 依存 | 生物由来原料 | 物理リスク | 急性 | 3 | 3 | Medium | 養殖場の環境変化によ魚病棟の感染リスクの高まりに応じて薬剤使用量の増加及び管理コストの増加、品質の低下が収益性の低下につながる。 | 2 | 2 | Medium | 養殖場の環境変化による魚病等の感染リスクの高まりに応じて薬剤使用量の増加及び管理コストの増加が収益性の低下に寄与する(薬剤使用は市場に重要視されない。) | |
| 慢性 | 3 | 4 | High | 海洋の天然資源量は減少しており、また漁獲制限も強化されるため、非食用魚の漁獲量は減少すると想定される。 そのため天然由来の飼料の調達もしくは、代替飼料の開発・調達にコストを要し、収益性が悪化する。 | 3 | 4 | High | 海洋の天然資源量は減少しており、また漁獲制限も強化されるため、非食用魚の漁獲量は減少すると想定される。 そのため天然由来の飼料の調達もしくは、代替飼料の開発・調達にコストを要し、収益性が悪化する。 | ||||
| 水質(海水) | 急性 | 3 | 4 | High | 養殖場の環境変化により養殖魚の生育が悪化し、収益性が一定程度減少す る。 | 3 | 4 | High | 養殖場の環境変化により養殖魚の生育が悪化し、収益性が一定程度減少する。 | |||
| 水流(海水) | 急性 | 4 | 2 | High | 気象災害によって養殖場は壊滅的な被害を受け、施設や生物資産の復旧に相応の期間が必要となる。 | 4 | 2 | High | 気象災害によって養殖場は壊滅的な被害を受け、施設や生物資産の復旧に相応の期間が必要となる。 | |||
| 洪水 | ||||||||||||
| 大気・地盤 | ||||||||||||
スケソウダラ漁業・養殖における採用シナリオの機会分析結果
機会について、スケソウダラ漁業はシナリオ#1、#3、養殖はシナリオ#2、#3、共通するものは#1,、 #2、#3 全てのシナリオを用いて分析しました。その結果、シナリオ#1 または#2 で消費者がサステナブルな商品を好んだ場合、当社の機会は大きくなると評価した一方で、消費者へサステナブルな商品が浸透しなかった場合の当社への財務インパクトは限定的なものに留まると想定されます。以上より、サステナブルな商品の市場への浸透が、当社の財務インパクトにポジティブに貢献すると考えました。
表 採用シナリオの機会分析結果
| 機会のカテゴリー | 期待される機会 | シナリオ#1
 |
シナリオ#2
 |
シナリオ#3
 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機会 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | 機会 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | 機会 大きさ |
発生 可能性 |
財務 インパクト |
マルハニチロの見解 | |||
| スケソウダラ漁業 | 市場 | より環境負荷の低い商品を求める消費者の志向の変化による、市場開拓や評判向上に起因し た、売上増加の機会 | 4 | 4 | High | エシカルな市場が急成長していくなかで、自社のサステナブル製品の需要が高まり、大き な機会が生じると判断 | 1 | 1 | Low | サステナブルな商品需要に顕著な変化がなく、引き続き市場へアピールを続けるものの、売上 への寄与は限定的 | ||||
| 資源効率 | 環境負荷の低い漁業による、持続可能な調達の促進に起因する、漁業ビジネスの安定化 | 3 | 4 | High | 厳格な法令順守の元実施される持続可能な漁業により、海洋資源量が維持され、ビジネスの安定化に寄与する。 | 3 | 2 | Medium | 厳格な法令順守の元実施される持続可能な漁業により、海 洋資源量が維持され、ビジネスの安定化に寄与する。 但し、海水温上昇などの外的要因による資源量の減少を防ぐことは容易ではなく、コストメ リットは限定的な可能性があ る。 | |||||
| 製品とサービス | 廃棄原料(残渣)をミール (魚粉)へ有効利用することによる、市場開拓や評判向上に起因した、売上増加の機会 | 2 | 3 | Medium | 漁業規制の強化や人口増加を背景に、養殖魚および養殖飼料の需要が増加し、サステナブルな魚粉の需要が 拡大する。 | 3 | 3 | Medium | 天然資源量の減少に伴い、養殖魚および養殖飼料の需要が増加する背景のもと、魚粉の需要が拡大する。 | |||||
| 養殖 | 資源効率 | 飼料転換率(要注釈)の向上により、天然資源の使用量を削減することに起因する、コスト削減 | 3 | 3 | Medium | 飼料生産部門は保有していないため、他社と比較して大きく先進的・革新的な技術開発が進むとは考えにくいが、ある程度の機会 は期待できると判断 | 3 | 3 | Medium | 飼料生産部門は保有していないため、他社と比較して大きく 先進的・革新的な技術開発が進むとは考えにくいが、ある程度 の機会は期待できると判断 | ||||
| 製品とサービス | 先行的な投資による、市場地位の確立に起因した、売上増加の機会 | 3 | 3 | Medium | エシカルな市場が急成長していくなかで、自社のサステナブル製品の需要が高まり、大きな機会が 生じると判断 | 2 | 2 | Low | サステナブルな商品需要に顕著な変化がなく、投資効果はは 限定的 | |||||
| 市場 | より環境負荷の低い商品を求める消費者の志向の変化による、市場開拓や評判向上に起因した、売上増加の機会 | 3 | 3 | Medium | 天然資源量の減少に伴い養殖魚の市場は拡大し、特に自社のサステナブル製品の需要は大きく成長すると考えられる。 | 2 | 2 | Low | 天然資源量の減少に伴い養殖魚の市場は拡大する。一方でより安価な商品を選好する市場においてはサステナブル商 品のシェア拡大は限定的 | |||||
| 市場 | 海水温上昇に伴う魚種の変化 により、代替たんぱく原料(細胞培養)での売上増 | 4 | 4 | High | エシカルな市場が急成長していくなかで、サステナブル製品の需要が高まり、大きな機会が生じると判断 | 3 | 3 | Medium | 全体的なタンパク質需要の増加を背景に代替たんぱく質の需要も増加。消費者はコストパ フォーマンスを優先するため、低 価格高品質であれば売り上げの向上に寄与する。 | |||||
| 市場 | 養殖環境向上への投資による、生産量の増加に起因した、売上増加の機会 | 3 | 3 | Medium | エシカル消費が進んだ市場においては、投資コストの価格転嫁が受け入れられ、生産量の向上 が売り上げに寄与する。 | 2 | 3 | Medium | 投資コストの価格転嫁が受け入れられず、コストメリットは限定的 | |||||
| 共通 | 市場 | 企業評価格付けの向上による、投資家からの評価向上に起因した、株価上昇の機会 | 2 | 3 | Medium | (漁業) ESG評価は投資意思決定に大きく影響し、株価の上昇に寄与する。 | 3 | 3 | Medium | (養殖) ESG評価は投資意思決定に大きく影響し、株価の上昇に寄与する。 また、資源量の減少とたんぱく質の需要増加が追い風となり、食品セクターへの投資意欲が高 い。 | 1 | 3 | Low | ESG評価の投資意思決定への影響はさほど重要ではなく、株価への寄与は限定的。 |
| 資本フローと資 | グリーン投資市場へのアクセスに よる資本コストの削減 | 3 | 3 | Medium | 資本コストへのインパクトは限 定的と想定した | 3 | 3 | Medium | 資本コストへのインパクトは限定 的と想定した | 1 | 2 | Low | シナリオ設定として、投資家は 財務的な成長を優先する | |
| 評判資本 | ブルーカーボンクレジットの開発や海洋プラスチック汚染の除去等地域ステークホルダーとの協働による、市場開拓や評判向上に起 因した、売上増加の機会 | 3 | 3 | Medium | ESG評価は市場においても 重要視され、売り上げに一定程度寄与する。 | 3 | 3 | Medium | ESG評価は市場においても重要視され、売り上げに一定程度寄与する。 | 1 | 2 | Low | 市場はコストパフォーマンスに影響しない取り組みを考慮しな い。 | |
リスクと影響の管理
当社グループが事業活動を行ううえでの全社的なリスク管理については、法務・リスク管理部を中心 に、マルハニチロ㈱各部署やグループ各社のリスク管理責任者、リスク管理担当者が連携して取り組む体制を整えております。「環境」ならびに「サステナビリティ関連」の短期的かつ影響度の高いリスクについては、毎年実施されるリスクマネジメントプログラムによりリスクの抽出から分析そして対応策の検討が行われ、経営会議に報告されます。
加えて ESG・サステナビリティに関連する中長期的なリスク・機会に対しては、サステナビリティ推進委員会において管理し、討議しております。特に気候変動と生物多様性におけるリスクは重要リスクの一つとして考慮しており、TCFD フレームワークに基づくシナリオ分析や TNFD の LEAP アプローチによって分析・評価したリスクと機会、対応策などについて管理・討議しています。
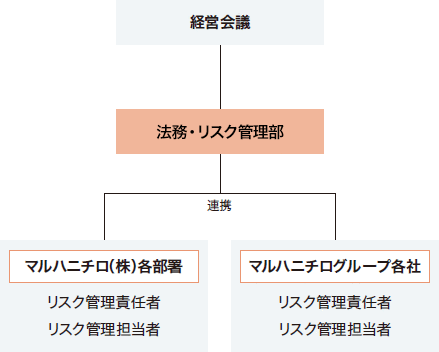
指標・目標と関連する実績(Prepare)
リスク・機会分析に基づく指標と目標
マルハニチロは特定したリスクおよび機会に関する重要課題について、課題解決のために以下の指標・目標(KPI)を設定しています。これらの KPI を達成するための取組みにより、リスクの低減と機会の最大化を目指していきます。
表 マルハニチログループリスク分析結果への対応
| 重要な依存・影響および リスクに対するマルハニチロの見解 |
リスクに関わる重要課題 | 重要課題への基本的な考え方 | マルハニチロの取組み | 関連するKPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スケソウダラ漁業 | 資源管理はかなり厳格に行われているものの、海水温の上昇等、外部要因による資源量の減少はは当社へのマイナスの財務インパクトにつながり、また漁獲エリアの地域住民の方々の資源アクセス制限にもつながると考えられる。 | 海水温の上昇など、外部的な影響による資源量の低下 | 厳格な漁業管理に基づく事業活動を継続しつつ、国際的なイニシアチブへの参画などを通して外部的な影響による資源量の低下の防止にも努める | 米ベーリング海の厳格な漁業規制(漁獲海域、漁獲枠、時期、漁具、漁法の制限など)に沿った操業 | MSC認証取得漁業(米ベーリング海・カムチャッカ西)由来水産物の調達 | 水産資源調査の実施 | SeaBOSでのタスクフォースIVにおける取組み | ・2030年度末までに取扱水産資源の資源状態確認率100%(グローバル連結子会社全体) |
| 漁業従事者の権利の保護 | 当該資源は地域住民の重要な資源であるため、厳格な漁業管理に基づく事業活動を継続する | 米ベーリング海の厳格な漁業規制(漁獲海域、漁獲枠、時期、漁具、漁法の制限など)に沿った操業 | MSC認証取得漁業(米ベーリング海・カムチャッカ西)由来水産物の調達 | 持続可能性に配慮した水産物の調達方針の策定 | ||||
| 養殖 | 生物資本への依存に関わる因子によるリスクが大きく、重点的に対応が必要。 | 飼料に使用している天然魚資源量の減少 | 飼料中の天然魚資源の資源量把握が急務であり、資源量把握後は各資源の適切な資源管理に努める | 水産資源調査の実施 | 養殖場の自主管理基準の制定 | ブリ・カンパチのASC認証取得 | ・2030年度末までに取扱水産資源の資源状態確認率100%(グローバル連結子会社全体) ・2027年末までにグループ内全養殖場で 認証レベル管理体制の構築(国内グループ連結子会社) |
|
| 赤潮等による海水水質の悪化への対応 | 海水水質や海水温の変化への対応は事業継続において重要であり、大型浮沈式銅合金生簀の導入等、新たな養殖技術の発展が重要である | 養殖魚の飼育環境に配慮した大型浮沈式銅合金生簀の導入 | ||||||
| 気象災害へのレジリエンス強化 | 本重要課題への対応においては養殖技術の発展が必要である | 養殖魚の飼育環境に配慮した大型浮沈式銅合金生簀の導入 | スギの養殖の開始 | |||||
表 マルハニチログループ機会分析結果への対応
| 機会に対するマルハニチロの見解 | リスクに関わる重要課題 | 重要課題への基本的な考え方 | マルハニチロの取組み | 関連するKPI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スケソウダラ漁業 | シナリオ#1のように進んだ場合、当社へのプラスの財務インパクトは大きい。資源管理は厳格に行われているため、マーケット環境がネイチャーポジティブへの移行に対して前向きになることがキーポイント。 | エシカル市場の醸成 | エシカル市場の醸成のため、サステナブルシーフード※の消費者への理解浸透が重要 | 健康価値創造と持続可能性に貢献する食の提供 | ・2030年度末までに水産製品 ・水産物を含む全製品のサステナブルシーフード(持続可能な認証製品)売上比率15%以上(マルハニチロ(株)) |
||
| 資源量の維持 | 厳格な漁業管理に基づく事業活動は事業の安定化に寄与する | 米ベーリング海の厳格な漁業規制(漁獲海域、漁獲枠、時期、漁具、漁法の制限など)に沿った操業 | MSC認証取得漁業(米ベーリング海・カムチャッカ西)由来水産物の調達 | 持続可能性に配慮した水産物の調達方針の策定 | |||
| 養殖 | シナリオ#1のように進んだ場合、当社へのプラスの財務インパクトは大きい。マーケット環境がネイチャーポジティブへの移行に対して前向きになった場合にその需要に応える体制づくりが重要。 | ASC認証取得の拡大 | シナリオ#1のように進まなかった場合、投資コストの価格転嫁が見込めないため、コストメリットは限定的となるものの、マーケット需要に応える供給体制の準備が重要 | 水産資源調査の実施 | 養殖場の自主管理基準の制定 | ブリ・カンパチのASC認証取得 | ・2030年度末までに取扱水産資源の資源状態確認率100%(グローバル連結子会社全体) ・2027年末までにグループ内全養殖場で認証レベル管理体制の構築(国内グループ連結子会社) ・水産物を含む全製品のサステナブルシーフード(持続可能な認証製品)売上比率15%以上(マルハニチロ(株)) |
| 細胞性水産物の事業化 | マーケット需要に応える供給体制の準備が必要 | UMAMI Bioworksと細胞性クロマグロの開発 | |||||
※Global Sustainable Seafood Initiativeで承認された認証水産物(MSC認証、ASC認証、BAP認証、MEL認証等がある)
中核開示指標
表 中核開示指標に基づく情報(スケソウダラ漁業・養殖)
| Global/Sector | TNFD Metric No. | サブカテゴリー / ドライバー |
指標 | 現状 |
|---|---|---|---|---|
| Global | ー | 気候変動 | GHG排出量 | 環境データ集 (国内G) |
| C1.0 | 陸域・淡水域・海洋の利用の変化 | 空間のフットプリント(km2) |
FAO 61,67区域 (スケソウダラ漁業) 56,439m2(陸上面積) 389,002m2(漁場面積) (養殖) |
|
| C2.1 | 汚染/汚染除去 | 排水 | 環境データ集 (国内G) |
|
| C2.2 | 有害/非有害廃棄物の種類別発生重量 | 環境データ集 (国内G) |
||
| C3.0 | 資源の使用や補給 | 水源を考慮した水不足地域からの取水量および 消費量(m3) |
環境データ集 (国内G) |
|
| C3.1 | 資源の使用や補給 | 陸域・海洋・淡水域 から調達するリスクの 高い天然商品の量 |
取扱水産物の資源調査結果 | |
| 持続可能に管理された資源から捕獲された総漁獲量の割合 | 取扱水産物の資源調査結果 | |||
| C4.0 |
侵略的外来種とその他 | 意図的でない侵略的外来種(IAS)の持ち込みに対する対策 | 取扱い分全てMSC認証漁業 (スケソウダラ漁業) |
|
| C5.0 | 自然の状態 | 種の絶滅リスク | 取扱水産物の資源調査結果 | |
| C7.0 | 移行リスク | 自然資本関連移行リスクに対して脆弱であると評価された資産、負債、収益、費用の割合 | シナリオリスク分析結果 (スケソウダラ漁業) (養殖) |
|
| C7.1 | 物理的リスク | 自然資本関連物理リスクに対して脆弱であると評価された資産、負債、収益、費用の割合 | ||
| C7.2 | 移行リスク - 責任 | 自然に関する負の影響について、報告年に発生した重大な罰金や訴訟の内容と対応費用 | 過去3年間該当なし (スケソウダラ漁業) 過去3年間該当なし (養殖) |
|
| C7.3 | 機会 | 機会の種類別の資本的支出・資金調達または自然関連の機会に向けて展開された投資額 | ブルーボンドの発行 (MN) |
|
| C7.4 | 機会 | 水産物を含む製品のうち、GSSIによって承認された認証製品の売り上げ比率 | 2024年度6.4% (MN) |
|
| C7.4 | 機会 | ー | 取扱い分全てMSC認証漁業 (スケソウダラ漁業) |
※対象組織を略称で記載
MN=マルハニチロ㈱、国内G=国内グループ連結会社、G全体=グローバル連結会社、海外G=海外グループ連結会社