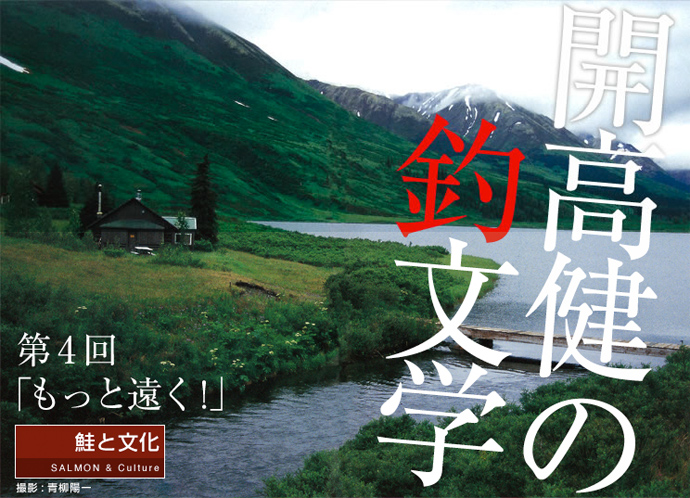|
(中略)
アラスカの海ではなくて川でのサケ釣りを私なりに評価してみると、これはもっぱらブリストル湾地域の川での経験だが、つぎのようになる。筆頭は何といっても偉大なキングで、これの大物との格闘はしばしば頭からのめりこむようなファイトになり、そのあとは心身を吸収されてへとへとになり、素晴らしいという呟きすら洩れるゆとりがない。アラスカの釣師が“フィッシュ”といったらそれはキングのことだといわれてるくらいである。この魚は数が少ないし、州の象徴として保護されているので、スポーツ・フィッシングで釣っていい匹数は厳重に制限されているから、いよいよ男たちの狂熱がかきたてられる。
この魚は闘争本能が一匹ずつ異なるという説があり、ヒットの瞬間瞬間にその場その場で神速に竿さばき、リールさばきをやらねばならず、この点、さらに男たちの尊敬と情熱が吸収されるのである。 |
|
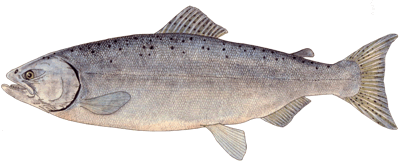 |
|
| マスノスケ、キング・サーモン |
|
| 二番めがシルヴァーである。これはキングよりも小さいけれど満身に精悍なエネルギーがつめこまれていて、ジャンプまたジャンプ、最後の最後までたたかいぬき、岸に寄せて横返しになっても油断ができない。ジャンプして頭をふられるとたいてい鈎がぬけるので、糸はぜったいに張りつめておかなければならない。鈎をはずされないよう、ジャンプされないようにするには、ヒットした瞬間に竿をリールまで水につっこんで糸をなるべく斜め上からひっぱらないようにすれば効果があるといわれている。これはシルヴァーだけではなくて、ジャンプする魚なら何についてもいい方法である。しかし、私としては逃げられてもいいから魚のハイ・ジャンプを見たいという気持がある。シルヴァーは全身がつややかな白銀に輝やく美しい魚で、それが飛沫を蹴たてて川面を跳ねまわる光景には恍惚となる。この魚の場合には頭からのめりこまないで、諸相を鑑賞し味わいつつファイトができる。しかし、すべての魚とおなじくこの魚も気まぐれで、ある日は一匹ずつがあますところなく跳躍してくれたのに、つぎの日はまったくやらないで、イワナ類やチャム・サーモンのようにもっぱら水中だけでたたかうということがある。 |
|
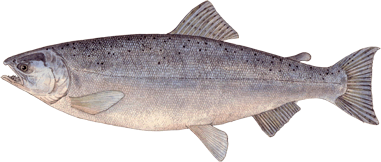 |
|
| ギンザケ、シルヴァー・サーモン |
|
| 三番がレッドで、四番がチャムである。レッドの不思議さについてはつぎに書くが、チャムというサケは力持ちではあるけれどジャンプしてくれないのでものたりない。このサケは日本で“新巻”となって登場するサケで、私たちにとってこれくらいなつかしい魚はないのだが、アラスカでは“ドグ・サーモン”と呼ばれる。味がまずいので犬の餌にする魚だというところだが、スポーツの対象としても面白くないので軽視され、それがドグ呼ばわりの一因となっている向きがある。この魚のおいしさについては今されら私がここに書くことはないので、省略させて頂くが、ドグ呼ばわりは片腹痛いと、声をあげておきたい。ところでたいていの人が気づかないでいらっしゃることで一言しておきたいのは日本のサケ缶の表示で、レッテルにごく小さく“CS”、“PS”とある。前者はチャム・サーモン後者はピンク・サーモンの略である。どちらがおいしいかは好みの問題だから、ここでは議論を避けるが、今度からスーパーへ行ったらよく眼鏡を拭いてCかPかを判別なさるとよろしい。 |
|
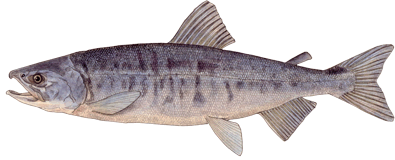 |
|
| シロサケ、チャム・サーモン |
|
| レッド・サーモンは川に入ってきたときは婚姻色で頭部が緑色、それ以下の体が暗赤色に染まる。この魚が大群で川をさかのぼっているところを空中写真でとると、川そのものが真紅に染められ、荒野のまっただなかに血が流れたようである。ビーヴァーの窓から見おろすと、あちこちからの川や湖でこの魚が集結しているところはまるで金魚の大群を見るようである。腹が厚く、肩がどっしりとして、なかなかいい体格の魚なのだが、空中から見おろすと、金魚にそっくりである。川では岸近く、湖では川の流れこみや流れだしのあたりに集結するが、ときには川も何もないただの湖岸にたくさん集結してるのを見ることもある。何十匹なのか何百匹なのか数えようもない団塊になっていることもあり、ときには三、四匹のこともある。 |
|
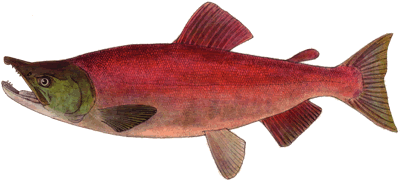 |
|
| ベニザケ、レッド・サーモン |
|
| ちょっと以前に出版されたサケ釣りの本を読むと、この魚はルアーでは釣れないか、またはたまにしか釣れないとされている。十年前にはじめてアラスカへサケ釣りに来たときも土地の釣師によくその話を聞かされ、自慢話はもっぱらキングとシルヴァーであった。しかし、今度はスポーツ・フィッシングとしてレッドの釣りを教えられた。それはもっぱら川での釣りで、これにはコルクまたはプラスチックで作ったサケの卵を使う。まんなかに穴があいていて、そこに糸を通し、鈎をつける。そして糸の上に小さなゴム管をつける。このゴム管に細い鉛筆のような鉛の棒をちょっとさしこむ。そのままつっこむと入りにくいが、ちょっと舐めて唾をつけると、するりと入る。これは岩に噛まれても強くひっぱれば鉛だけがぬけてあとは回収できるので賢い考案である。レッドはフラフラと流れてくる赤い、小さな玉を卵だと思って、そっと口にくわえる。これは卵を食べるためではなく保護するためではないかという説がある。インディアンの古い言い伝えにもそういう説があるそうである。急な流れのところで魚が綿のように軽くくわえるのだから、当りはきわめて感知しにくい。そこで、当りのあるなしにかかわらず、ここぞと思うあたりで竿をしゃくる。こういうあわせかたを日本では“カラあわせ”と呼ぶが、アラスカでは“インテンショナル・スナギング”、つまり、意図的なひっかけという。地区によっては川を監視員が歩きまわって釣師を観察し、あまりたびたびやってはいかんよと警告するところがある。この釣法はレッドだけではなくて、海から上がってきたニジマス、つまりスチールヘッドを釣るときにもおこなわれれる。(後略) |
|
| 注「その映画*」・・・チャップリンの黄金狂時代:アラスカの金鉱が発見され一攫千金を夢見る人々が押し寄せていた頃、ひとりぼっちの探鉱家チャーリーは、猛吹雪に襲われ、一件の山小屋に転がり込んだ。だが、そこにいたのは、指名手配中の凶悪犯ブラック・ラーソンだった。ゴールド・ラッシュに湧くアラスカを舞台に、人間たちの剥き出しの欲望を、絶妙なギャグと卓越したストーリーで描く。 |
|