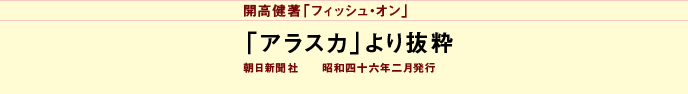 |
私はベッドによこになり、ジンくさい雑貨屋の主人の息やエスキモーのだみ声を耳のうしろのあたりに漂わせながら、
東京から持ってきた原民喜(はらたみき)の短編集を読みつづけた。毛布にはあぶらっぽい白人の体臭とバターの匂いがしみこんでいたが、よく磨かれた単語でつづられた、つつましやかで清潔な狂気の文章は東京でよりもはるかにしみじみと私に浸透してきた。 |
|
| B社の文学雑誌に連載しているエッセーにこの人の原爆体験の作品のことを書こうとしたのだが、二ヶ月間、私は字が書けなかったのである。K社の文学雑誌に連載している隔月ごとのエッセーも休んでしまったし、B社のこの仕事も休んでしまった。去年の晩秋頃から冬いっぱい、そして今年の春おそくまで私はとらえようのない憂鬱症にたれこめられて、はなはだしい衰弱に陥ちこんでいた。私の場合にはその発作は珍しいことではなく、小さいのはいつでもサイクルをつくって巡ってくるが、大きいのはここしばらくあらわれなかったのである。人と会ったり話をしたりするとき私はにこやかに談笑できて正常そのものなのだが、そのあとでひとりになると、たちまち人や物や言葉から地崩れを起してすべりおちてしまうのである。家にたれこめ、毎日、ただ朦朧(もうろう)と眼をひらき、もっぱら鳥獣虫魚に関する本だけ読み、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、いっさいを切断してすごした。バーにも出没せず、パーティーにも出ず、午後おそくになると二階の窓ぎわで海綿のようにウィスキーを吸った。黄昏が手に沁(し)みてくるのを感じながらすわっていると、どこか野菜畑のあたりでワッ、ワッと拍手喝采(かっさい)する声のあがるのが聞こえてくるようであった。 |
|
| 茅ヶ崎市 開高健記念館:開高さんの執筆机(開高健記念館提供) |
|
|
いつかこれに似たことが起こったときは和歌山県の潮ノ岬(しおのみさき)の突端まで走り、小さな旅館の二階の部屋にこもって海を眺めながら一週間か十日、ただウィスキーだけ飲んですごしたことがあった。そのあとでたまたまいい素材と出会うことができたので、ただ自分の憂鬱を晴らしたい目的だけで速歩の文体でかけぬけるようにして長篇を書いた。医者にも見せず、病院にも入らず、薬ものまず、どうにかこうにか迫り浸してくる潮をうっちゃることができたのである。
けれど、素材と出会えず、自身が燃焼できないときは、とらえようのない焦燥と憎悪にみたされたまま、部屋のすみにウィスキーを吸いこんだ海綿のかたまりとして落ちているしかなかった。今回のがそれであった。いわゆる“ブランク”でないことは、かなりわかっていて、むしろ私は発作と意識していた。晩秋頃からそれが明瞭になってくると、私は毎日、窓ぎわでウィスキーを飲みつつ、スモッグで腐って硫酸のようになっている低い夕空を眺め、原民喜の本を伏せてしまい、アラスカへいこう、アラスカの荒野の川でサケ釣りをしよう、と思いつめていた。(抜粋) |
|
 |
|
| 茅ヶ崎市 開高健記念館:書斎(開高健記念館提供) |
|
|
| 一撃。二撃。三撃。竿がきしんで水へつきそうになった。私はふるいたって竿をあおってあわせたが、すごい剛力。竿がたたない。たちまちリールが鳴って糸を吐きだしはじめた。「大使(アムバサダー)5000C」は低い声で鋭く唸(うな)りはじめた。竿がぶるぶるふるえる。きしむ。糸が川風をこすってヴァイオリンの高音部のように唸りだした。かかったのだ。魚は剛力をふるって下流へ、下流へと走りだした。私は竿にしがみついたまま、砂泥から足をひきぬき、水のなかを小走りに走った。魚を追って。下流へ。下流へ。 |
|
「おーい、おーい」
とも、
「あきもとォ」
とも、
「かかった、かかった」
とも私は叫んだようである。 |
|
けれどはるか上流に秋元啓一は小さな棒となって川に刺さったきりである。走りながら私は蒼(あお)くなった。この竿は替穂がついていて一本は“ズーム1”といって細く、マス用である。もう一本は“ズーム2”といって太く、サケ用である。ところが昨夜パーキーとボートで流し釣りをしているときに、きっとスクリューに糸が巻きこまれたのだと思うが、ひどい力でひきこまれ、あわせるすきもなく舟べりに竿があたったはずみに、“ズーム2”が折れてしまった。だから今日は“ズーム1”を持ってきたのだった。つまり、いま、マス用の竿でサケとたたかわねばならないのである。それはキィキィとたわみ、きしみ、ふるえた。モノの本でたっぷり読みためた知識は一瞬に蒸発してしまった。
醜怪な妄念も消えてしまった。輝く惑乱が私を占めた。
魚は水しぶきをたてて二度、跳躍した。一度は高く、二度めは低かった。そこで道糸がゆるむと鈎がはずれる。私はリールをいそがしく巻いた。それきり魚は跳ねない。赤銅色に輝くブリがマグロのように太い胴が眼にのこった。
持久戦がはじまった。右手の指がスター・ドラッグ(星型のブレーキネジ)をじりじりと締めたり、ゆるめたり、ハンドルを巻いたり、耐えたり、いそがしく往復しはじめる。
広大な川にたった一本の糸が刺さり、バターの柔らかいかたまりを鋭いナイフが切るように、水を右へ左へと切る。走る。ふるえる。魚が疲れるのを待って“パンピング”に入る。竿といっしょに体をたてたり、たおしたりしながら糸を巻くのである。ゆっくりと。注意深く。優しく。けれど断固として譲らずに。
下流で釣っていた村の若者がいちもくさんに走ってきた。自分の竿を捨て、腰から手鉤(ギャフ)をひきぬいて、走ってきた。彼は岸で用心深く待ち、魚がくたびれきって浅瀬へよってくるのを見てから、水のなかへたちこみ、手鉤を使った。一度失敗して、二度目に成功した。鋭い鉤が魚の胴深く刺さり、一挙動で岸へひきずりあげられた。どすッ、どすッと跳ねるたびに、口もとに刺さった靴べら大のスプーンがおどり、石にあたってガチャガチャと鳴った。
竿をすててかけつけ、
「キング?」
とたずねると、
若者は、
「そうです」
といって微笑した。
この魚は六千キロのかなたから故郷の川を匂いでかぎあてて誤たないといわれているが、海から川に入って二、三日から一週間ほどすると、体に赤銅色があらわれる。ニジマスが海へおりたのを“スチールヘッド”と呼ぶが、そのときは頬から胴へかけてのあの輝かしいバンドが消え、ふたたび川に入ってくると、また虹(にじ)の帯があらわれるそうである。どうして淡水は住人を華麗にするのだろうか。(抜粋) |
|
|


