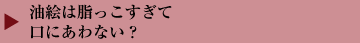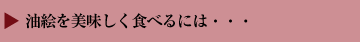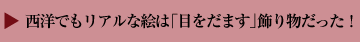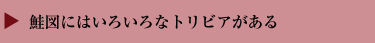鮭と文化


みなさんはきっとどこかで、とても写実的に塩ジャケを描いた縦長の油絵をみたことがあるにちがいない。縄でぶらさげられ、半身の一部を切り取られて赤い身がみえる、そんな鮭図を。
何のためにここまでリアルに塩ジャケを描きこまなければいけないのだろうか、と不思議に思いながらも、塩ジャケに寄せる画家の熱い想いが伝わってきて、感動した覚えがあるのではないだろうか。じつはこれには、「西洋画事始め」ともいえる興味深い話がある・・・
塩ジャケを描いた図は、10枚以上もあるといわれ、明治の初めに制作された。描いた画家も一人ではないと考えられるが、すくなくとも元祖は高橋由一という日本人洋画家である。そこに実物があるのかと勘違いしてしまうほどリアルな油絵を制作することは、西洋美術の長い伝統になっていたが、幕末の頃、その西洋画を見て、日本美術にない生々しいほどのリアリティーに驚いたのが高橋由一だった。江戸の洋書調所画学局にはいって洋画を学んだ由一は、明治維新後、博覧会に油絵を出品するようになり、立体感と物質感にあふれる西洋画を日本に普及させる努力をつづけた。
でも、浮世絵などのさらりとした日本画に慣れた庶民にすれば、なにやらものものしくて重苦しい油絵は不気味なだけだったし、日本家屋には額縁に入れた西洋画を飾る壁もなかった。絵といえば床の間に掛け軸として掛けるものしか思い浮かばない。したがって、西洋画のなかでもとくに脂っこい「油絵」は気味悪がられるだけで、人気も上がらなかった。
高橋由一(1828~1894)「鮭」
明治10年(1877)頃 紙・油彩
140.0×46.5cm 重要文化財
東京藝術大学所蔵
では、どうしたら、脂っこい油絵の魅力が日本人に伝わるだろうか。高橋由一は台所で見る豆腐や魚やカツオブシなどの食材を描くことを思いついた。油絵は脂っこいものなのだから、心というよりも目玉とか食欲に訴えればいいのではないだろうか。そうだ、食べ物を描けばいい! これなら、いつでも写生できるし、実物が家の中にゴロゴロしているのだから、実物そっくりの絵を飾っておいても違和感がない。そそっかしい人は、ホンモノだと勘違いして、ゴクンと生唾でも飲んでくれるかもしれない。食欲が湧く絵! これはすごいことになりそうだ、と由一は思ったにちがいない。
また、絵のサイズも解決しなければいけない問題だった。カンバスの四角な形でなく、横に長い引き戸や欄間の形、あるいは縦長の掛け軸みたいにすれば、油絵だって日本間におさまるかもしれない。そんなわけで、由一が試みたうちいちばん気に入ったのが、台所にかけてある塩ジャケを描いた図だった。なにしろ、これらの絵を柱に掛けてみたら、薄暗い台所などではホンモノがぶらさがっているとしか見えないのだ。こうして、由一は油絵を日本の家に馴染ませるための切り札を、鮭図に見出したのだった。
おもしろいことに、西洋にも由一が描いたのとそっくりな干物や肉や食材の絵がある。これらは「静物画」と呼ばれる。17世紀頃日本と交流していたオランダを中心に大ブームになったリアルな写実画だ。家の中で見られる花瓶の花や食べ物、家具などを、徹底して写実的に描いてある。これらは、民家の壁に飾る絵として作られた。
ちょうどこの時代のオランダには、世界をまたにかけて莫大な富を手にした商人が出現し、しかも日々の仕事や暮らしに教会のミサと同じ価値をみいだしたプロテスタントが集まった。この新しい社会は家庭をハッピーで豊かにすることが生きる幸せと考えた。そこでまず、きれいな花や噴水がある庭ができた。別荘(ヴィラ)が立ち、家が情報交換とお付き合いの場になった。宴会もさかんになった。家には花瓶が飾られ、食卓には美味しいワインや料理がいっぱいに盛られ、台所には干物や野菜などの食材があふれかえった。まさに幸福と豊かさの象徴だ。でも、花はすぐに枯れてしまうし、食べ物はどんどん腹の中に消えてしまうから、いつも補充しなければならない。そのとき思いついたのが、花や食べ物の「だまし絵」を作ることだった。今なら造花や作り物の果物を置いておく感じだろうか。
幸福と豊かさを演出するための絵、これなら庶民も家に絵を飾りたくなる。「静物画」はこうしてオランダに流行し、やがてヨーロッパ全体を巻き込むファッショナブルな写実アートになった。
すると、この「美味しい写実画」に新しい楽しみ方が加わった。宗教界の方でも、流行の絵を活用したくなって、寓意という手法を導入したのだ。寓意という技法は、「たとえばなし」というものに近い。「見立て」といってもいい。そもそも、豊かでハッピーな暮らしを象徴するために花やら魚やら肉やらを描いたこと自体が、「寓意」だった。これを道徳や信仰の教えに活用すれば、狭義の寓意となる。たとえば、ワインはキリストの血、白いユリは処女マリア、オレンジやリンゴは生命を生む大地の生産力、蝶や鳥は飛ぶので魂や霊、貝殻やトカゲは冷たいから死、蛇は悪魔、といった具合に。静物画が宗教的になるにつれ、、その背景はレンブラントの絵のようにぐんと暗くなって、黒バックに花や果物が光を浴びて浮かぶ神秘的な絵柄になった。これでオランダ人は、白ユリの絵を「マリア様」の絵として眺めることができるようになった。上から吊るされ、身を切られた塩ジャケなどは、さしずめ、十字架にかけられたイエスの寓意ということになるだろう。
そのようにして、「静物画」は、家に飾るための新しい絵となった。高橋由一が鮭図を描いた動機と、ほんとうによく似ていることに驚かされる。高橋由一は、まさにヨーロッパで行われたのと全く同じ方法、すなわち「静物画」によって、油絵を日本の民家にすべり込ませたのだった。
高橋由一作といわれているいくつかの鮭図を眺めてみよう。いろいろなことがわかってやみつきになる。 まずは東京藝術大学が所蔵する「鮭」。明治10年頃の作品とされているが、半身の腹部を切り取られており、台所のリアリティーがひしひしと伝わってくる。どこか、処刑されたキリスト像を見るように荘厳な味わいもあるところがすごい。だいいち、とてもおいしそうではないか。一切れ焼いて、お茶漬けにでもしたい感じがする。鼻曲がりだから、種類はシロサケ、新巻きに使われるスタンダード種だ。それから、口がガッと開いていることも、見逃せない。ああなるのは、縄を鰓に通してあるので、体の重みが下あごにかかってしまうからだ。その重みがずっと下まで行って、からだにシワが寄る。この絵の塩ジャケも下がシワだらけ!!なんというリアリティーなのだろう。
次に、山形美術館に寄託されている「鮭図」は、明治11年ごろ描かれたもの。背景が暗いので、オランダの静物画の影響下にあることが実証できると思う。この身もまた、血肉のように真っ赤だ。でも、口があまり開いていないし、からだにシワもない。ちょっと物理的におかしいが、たぶん、加工が上手にできた個体だったからだろう。
明治12-13年ごろの作とされる「鮭図」は、さらにおもしろい。口もガッと開いているではないか。なんと、この絵は細長い板の上に描かれていて、そのまんま乾物屋の看板に使われてもおかしくない。文字どおりのだまし絵だ。その効果をさらに生かそうとしてか、荒縄にタグがついている。読んでみると、「日本橋中洲町美妙館よる出」となる。日本橋中洲とは箱崎のとなりにある町のことと思われる。美妙館というのは、二葉亭四迷よりも早く言文一致体で小説を書いた明治初期の天才作家、山田美妙(やまだびみょう)を連想させるが、絵が描かれた年代ではまだ美妙は子供なので関係なさそうだ。由一の知り合いから届けられた塩ジャケだったのだろう。
つづいて、明治17年ごろの作といわれる「川鱒図」(神奈川県立歴史博物館所蔵)。この図はきわめておもしろい。この塩ジャケは頭でなく尻尾を荒縄で縛り、逆さにぶら下げてあるからだ。そのせいで、口はきれいに結ばれているし、からだにシワも寄っていない。ちゃんと実物を見て描いたにちがいない。そうだとすれば、塩ジャケの下げ方にはすくなくとも二種類のタイプがあったことになる。尻尾からぶら下げるタイプのほうは、その種類も「シャケ(シロサケ)」でなく「川鱒」になっている。カワマスは現在、アメリカから移入してきたブルックトラウトの和名になっているけれど、この移入種は明治35年以降でないと日本で見られない。したがってそれ以前に描かれた「カワマス」がどういう種を指したものか不明だが、逆さに吊り下げられていることには重要な情報がある。日本の塩ジャケはほとんどが頭を上にぶら下げる。このほうが乾燥が速くて確実に加工できるといわれる。頭がいちばん乾燥しにくいので、ここから腐りだすのを防ぐために、頭を上にするのだそうだ。
ところが、日本に一か所、わざわざ頭を下にして塩引き加工する地方が実在する。この絵は、その珍しい産地から来た塩ジャケをあらわしている。その産地がまた、塩ジャケの聖地といわれるところだったから、話はおもしろくなるわけだが・・・・・・、
今回は切りよく、ここまで、といたしとうございます。(つづく)

荒俣宏 作家
1947年東京生まれ。慶応大学法学部卒業後、日魯漁業(現マルハニチロホールディングス)に入社。コンピューター・プログラマーとして約10年間のサラリーマン生活をおくる。その間、紀田順一郎氏らと、雑誌「幻想と怪奇」を発行。英米の幻想文学などを翻訳しつつ、評論も展開。独立後は翻訳、小説、博物学、神秘学などジャンルを越えた執筆活動を続け、その著書、訳書は300冊に及ぶ。代表作に350万部を越える大ベストセラーとなった『帝都物語』(全6巻 角川書店)、古今の生き物に対する博物学の集大成といえる大著『世界大博物図鑑』(全7巻 平凡社)などがある。日本大学芸術学部研究所教授。近著に『読み忘れ三国志』小学館、『想像力の地球旅行』角川文庫、『イリュストレ大全』長崎出版など。