鮭なんでも辞典
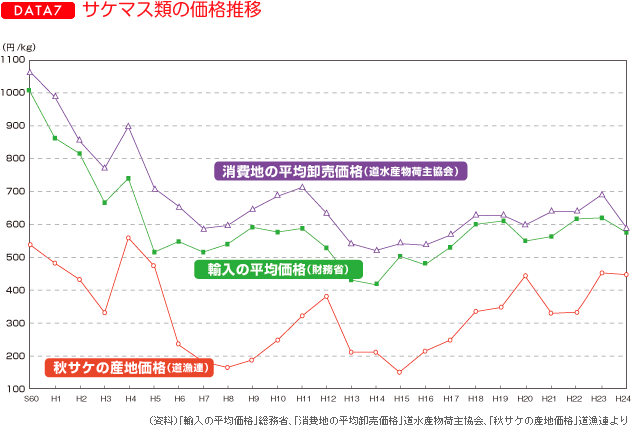 |
||
| (資料)「輸入の平均価格」財務省、「消費地の平均卸売価格」道水産物荷主協会、「秋サケの産地価格」道漁連より | ||
| 1989年(平成元年)当時のサケマス類の輸入平均単価は㎏1,000円ほどしていましたが、1993年(平成5年)以降は㎏500円台で推移しています。これはアラスカ産ベニザケがわが国のマーケットにおいてプライスリーダーで高価だった時代から、次第に主役は大量供給であるチリの養殖ギンザケやトラウト、ノルウェーの大西洋サケ(アトランティックサーモン)やトラウトに移っていたことを示しています。供給が増えると輸入総体の平均価格も安くなります。そして輸入の価格変動は消費地の卸売価格にも連動しています。 | 日本経済のバブル崩壊後、国民消費のデフレが長く続きましたが、サケマス市況は平成10年代半ばを底に回復傾向にあり2011年(平成23年)の輸入の平均単価は㎏628円となり、高値となりました。また、国内の消費地卸売平均価格も㎏698円と近年の最高値となりました。 しかし、2012年(平成24年)はチリを中心とした養殖サケマスの大量輸入で輸入単価は安価となりました。 |
|
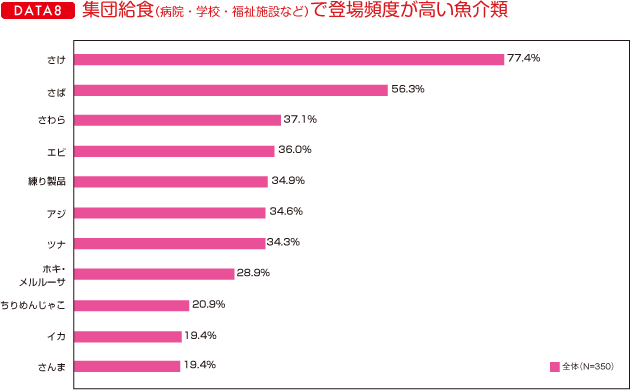 |
||
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(集団給食施設における魚食普及にむけた実態調査)」 社団法人 大日本水産会(平成22年3月発行)より |
||
| 【データ分析】 | ||
| 1) | 登場頻度が高い魚介類は、「さけ」が最も高く77.4%、次いで「さば」56.3%、「さわら」37.1 %であった。 | |
| 2) | 加工品である「練り製品」も34.9%であった。 | |
| 3) | さけ、さばにやや偏りがみられるものの、2割以上となる種類が多く、様々な種類の魚介類が利用されていることがうかがえる。 |
|
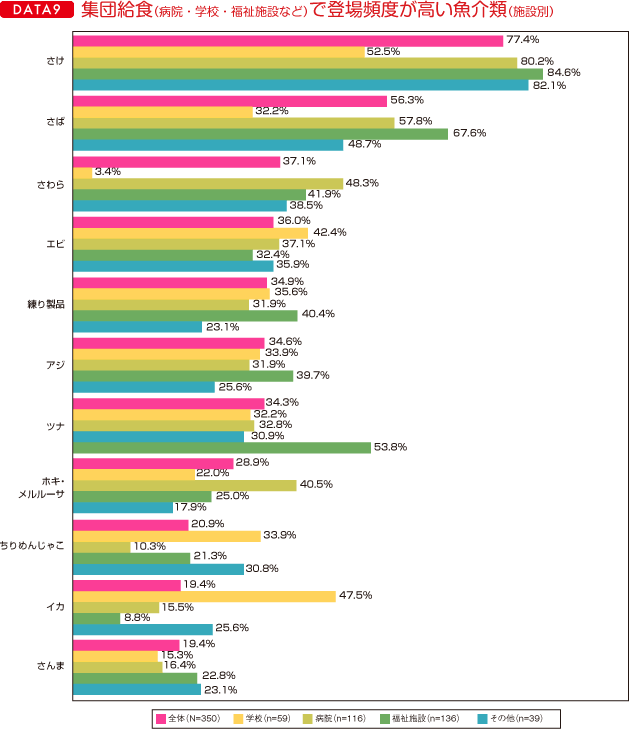 |
||
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(集団給食施設における魚食普及にむけた実態調査)」 社団法人 大日本水産会(平成22年3月発行)より |
||
| 【データ分析】 | ||
| 1) | 「施設別」に登場頻度が高い魚介類をみると、「学校」では他の施設と比較して「さけ」、「さば」、「さわら」が少なく、「ちりめんじゃこ」「イカ」が多い。特に3位の「さわら」は3.4 %にとどまり、他の施設と差異がみられる。 | |
| 2) | 一方、「エビ」「練り製品」「アジ」は施設による差異がみられなかった。 | |
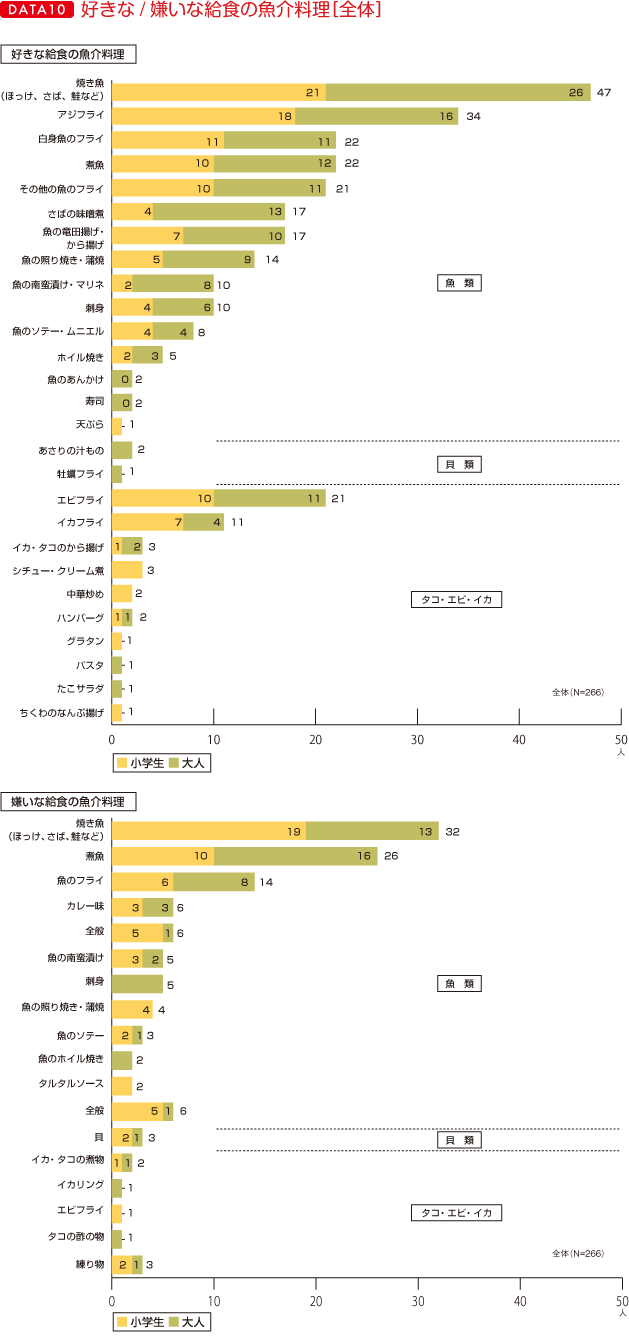 |
||
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(集団給食施設における魚食普及にむけた実態調査)」 社団法人 大日本水産会(平成22年3月発行)より |
||
| 【データ分析】 | ||
| 1) | 自由回答で、好きな/きらいな給食の魚介料理を聞いたところ、1位はいずれも「焼き魚」である。 | |
| 2) | 「あじフライ」はじめ、「白身魚のフライ」「エビフライ」「竜田揚げなど」、揚げ物が多く挙がっていた。 | |
|
|||||||||||||||||||
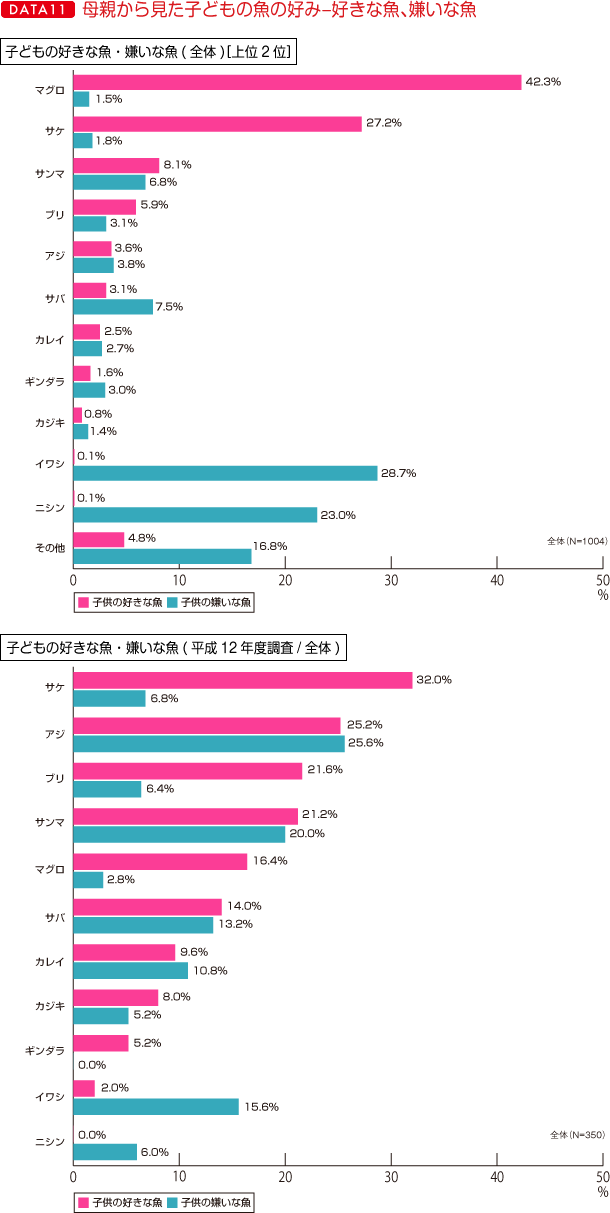 |
||
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(若年層対策調査:魚介類全般)」 食育啓発協議会 (社団法人 大日本水産会 平成20年3月発行)より |
||
| 【データ分析】 | ||
| 1) | 回答者である母親から見た子どもの好きな魚、嫌いな魚をそれぞれ上位2位まで尋ねた。 | |
| 2) | 好きな魚としては、「マグロ」が最も多く、続いて「サケ」という順であった。 | |
| 3) | 嫌いな魚は、「イワシ」、「ニシン」が圧倒的に多い。どちらも小骨が多い青魚である。 | |
| 4) | 平成12度調査と比較すると、好きな魚、嫌いな魚ともに、上位に変動がみられる。 | |
|
|||||||||||||||||||
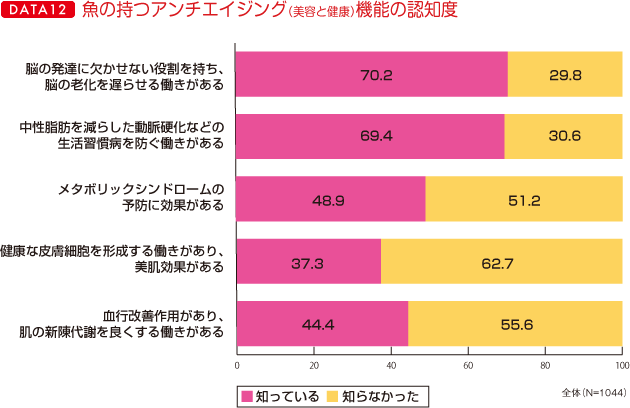 |
|
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(魚とアンチエイジング(美容と健康)に対する受容度調査)」 社団法人 大日本水産会(平成21年3月発行)より |
|
| 【データ分析】 | |
| 1) | 魚の脂に含まれる「DHA(ドコサへキサエン酸)」や「EPA(エイコサペンタエン酸)」にアンチエイジング機能があることについて、それぞれ知っているか尋ねたところ、「脳の老化を遅らせる働き」や「中性脂肪を減らし生活習慣病を防ぐ働き」については、全体の約7割が「知っている」と認知度は高い。 |
| 2) | 「メタボリックシンドロームの予防に効果がある」は48.9%と半数を切っており、「脳の老化予防」や「生活習慣病予防」に比べると、まだ認知度は低い。 |
| 3) | 「メタボリックシンドロームの予防に効果がある」は48.9%と半数を切っており、「脳の老化予防」や「生活習慣病予防」に比べると、まだ認知度は低い。 |
| 4) | 特に、「美肌効果」という文言に対し、「知らない」と回答する割合が62.7%と高く、魚が「美肌」に結びつくというイメージは低いようだ。 |
|
|||||||||||||||||||
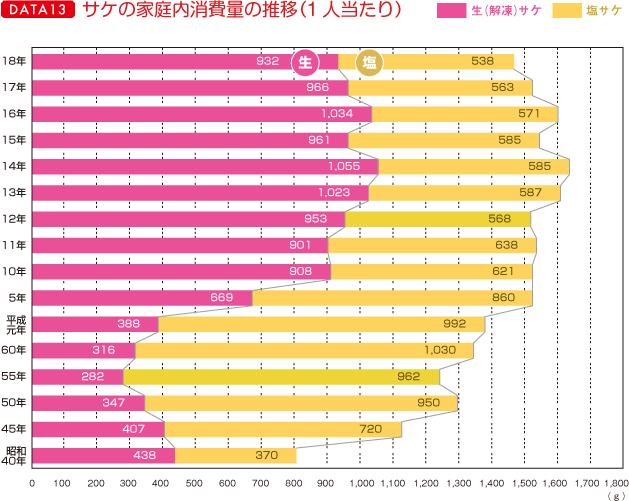 |
||
| (資料)総務省より | ||
| 総務省の家計調査年報データで、サケマス類の家庭での消費(購入)動向を見たのがこのグラフです。1970年(昭和45年)以降20年間は塩サケが主流でした。 本来サケは、塩蔵したものを年末年始を中心に食べる高級魚でしたが、供給量の増大にともない中級魚となり、経済発展による所得増で多く食べられるようになりました。しかし、経済の成長につれ「塩サケとご飯」といった従来の日本型食生活が薄れ、食生活が洋風化、多様化し、また減塩の健康志向から従来の塩サケが敬遠されるようになりました。 |
1985年(昭和60年)ころまでは塩サケの消費がサケ総体の7~8割を占め圧倒的に多かったのですが、その後の10年間で劇的に変化しています。それは国産の塩蔵品が減り、輸入の冷凍製品、つまり生(解凍)サケが市場に増えた結果によるものです。 | |
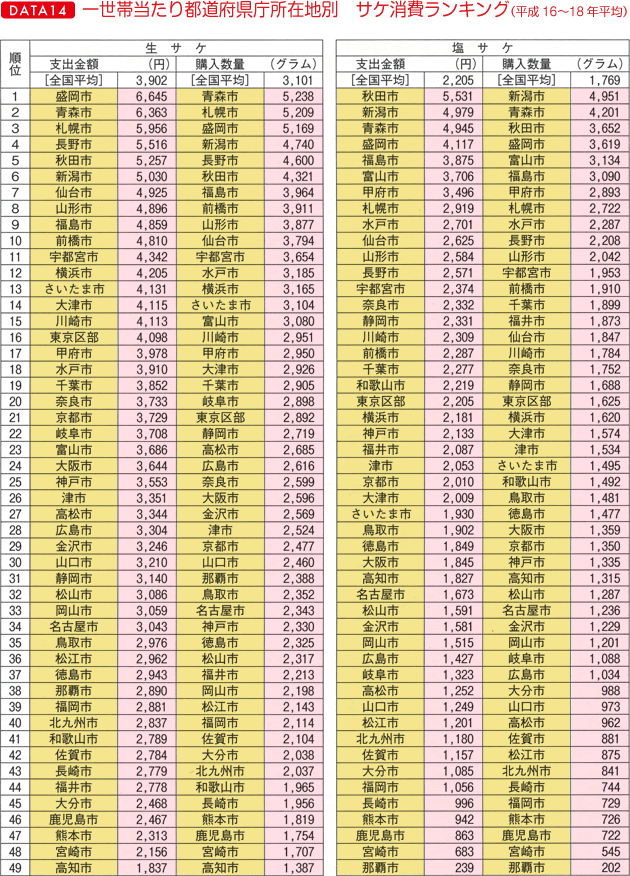 |
||
| (資料)総務省の家計調査より | ||
| 興味深いのがこの平成16~18年の「都市別サケ消費ランキング」です(総務省の家計調査)。生(冷凍)サケと塩サケの消費の違い。北日本と西日本の消費の違い。人口の多い都市と少ない都市の消費の違い。日本中のサケの消費地図が手に取るように浮かんできます。 | ||
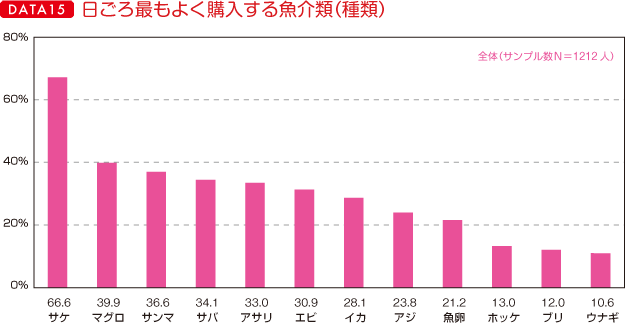 |
||
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(小中学生のいる家庭:魚介類)」社団法人 大日本水産会(平成17年3月発行)より | ||
| 【データ分析】 | ||
| 1) | 最もよく購入されている魚介類は「サケ」が圧倒的に多く、「マグロ」がその次に多い。 | |
| 2) | 一年を通じて最もよく購入する魚介類を選択肢から5つまで選んでもらい、約3分の2の人が「サケ」を選び全種類の中で突出していた。次いで、多い順に「マグロ」「サンマ」「サバ」「アサリ」「エビ」「イカ」であり、それぞれ3割~4割である。 | |
| 3) | 「ほとんど買わない」と答えた人は1人だけで、ほぼ全員が少なくともたまには魚介類を購入している。 | |
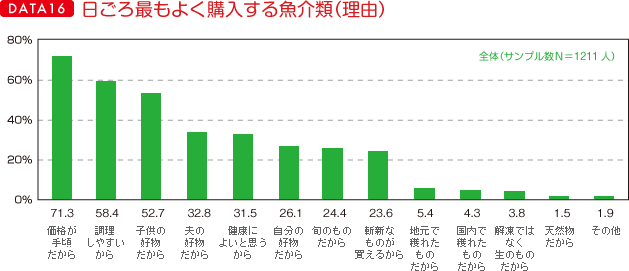 |
||
| (資料)「水産物を中心とした消費に関する調査(小中学生のいる家庭:魚介類)」社団法人 大日本水産会(平成17年3月発行)より | ||
| 【データ分析】 | ||
| 1) | 魚介類の購入理由としては、地元産、天然物といった魚介そのもの性質よりも、価格、調理のしやすさ、好みが優先されている。 | |
| 2) | 一年を通じて最もよく購入する魚介類について、なぜそれらの魚介類を購入するか理由を選択肢から5つまで選んでもらった。上位3つは「価格が手ごろだから」(7割)、「調理しやすいから」(6割弱)、「子供の好物だから」(5割強)。次いで、「夫の好物だから」と「健康によいと思うから」がそれぞれ3割弱であった。 魚介類の性質に関しては、「旬のものだから」、「新鮮なものが買えるから」は4分の1と比較的多いが、国内産、地元産、解凍でない、天然物、の4要素はいずれも約5%以下にとどまっている。 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 参考・引用資料 北海道定置漁業協会「サケマス流通状況調査報告書」(平成21年8月発行) 社団法人 大日本水産会「水産物を中心とした消費に関する調査(集団給食施設における魚食普及にむけた実態調査)」(平成22年3月発行) 社団法人 大日本水産会「水産物を中心とした消費に関する調査(魚とアンチエイジング(美容と健康)に対する受容度調査)」(平成21年3月発行) 食育啓発協議会(社団法人 大日本水産会)「水産物を中心とした消費に関する調査(若年層対策調査:魚介類全般)」(平成20年3月発行) 社団法人 大日本水産会「水産物を中心とした消費に関する調査(小中学生のいる家庭:魚介類)」(平成17年3月発行) |
|
|

