

缶詰に使われるサケは何種類ある?
いずれもサケ科サケ属に属している、おもに次の7種類です。カラフトマス(ピンクサーモン)、ベニサケ(レッドサーモン)、ギンザケ(シルバーサーモン)、シロサケ(サケ)、マスノスケ(キングサーモン)、サクラマス(ヤマメ)、ニジマス(サーモントラウト)です。

さけ缶に含まれる特徴的な成分は?
サケにはヒトの体内では合成されない9種類の必須アミノ酸がすべて含まれ、タンパク質の栄養価の判定基準「アミノ酸スコア」においては100点満点、またDHAやEPA、アスタキサンチンも含まれています。さらに缶詰の製法として加圧加熱殺菌をするため骨までやわらかくなり、骨由来のカルシウムも摂取できます。
(参考:文部科学省 日本食品標準成分表(八訂)
増補2023年アミノ酸成分表編)

サケとマスは同じなのか?
違うのか?
同じ仲間です。かつては、海に降りるものをサケ、淡水生活するものをマスと呼びましたが、その分類はきわめて曖昧です。キングサーモンは和名でマスノスケと呼ばれていますし、現在のベニサケにはベニマスと呼ばれた時代があります。

ブリキ缶に詰めたのはイギリス人
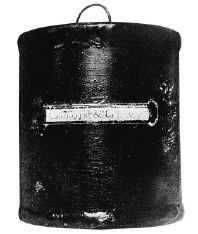
1810年、イギリス人のピーター・デュランによって、ブリキ缶による世界初の缶詰が開発されます。1820年代の缶詰は厚手のブリキを使用していたため、「斧とハンマーで開けてください」と記されていました。

「PINK SALMON」
の意味

原材料であるカラフトマスは、英語名でPink Salmon(ピンク・サーモン)と言います。発売当時からの名残で、イラストには「PINK」が記されています。

「白地に赤の3本線」の由来

日本人にとって“缶詰のアイコン”とも言える赤と白のストライプ。このデザインは、「あけぼの さけ」を作った堤商会(日魯漁業の前身)の、半纏にも記された模様に由来しています。

「さけ水煮」ってどんな調理?
カラフトマスを釧路の工場で切りそろえ、その身を食塩水につけ、肉を引き締めます(塩析)。それから水と一緒に缶に密封した後、レトルト釜に入れて加熱殺菌(蒸し煮状態)します。これが「煮る」という調理段階にあたります。つまり、長期保存できるようにするための加工が、そのまま「水煮」という調理になっているのです。

保存料などは一切入ってません!
缶詰が長期間保存できるのは、「密封」と「加熱殺菌」が完全になされているからです。缶詰内では酸化が起きないために食品が腐らず、長期間おいしい状態で保たれます。保存料も添加物も一切加えていません。添加する必要がないのが缶詰なのです。

缶の凹み、サビは大丈夫?

缶詰の内部は真空状態ですので、ぶつけると凹みやすくなっています。ただし缶蓋の巻締め部分が大きく変形したものは密封状態が保たれていないことがあり、注意が必要です。また、少々のサビは中身に影響することはありませんので、問題なく食べられます。

誰が最初に作ったの?

1910年、堤商会を起した堤清六と平塚常次郎がベニザケを輸出用缶詰にしたのが、最初の「あけぼの さけ」でした。ふたりはこれに、DAY BREAK BRANDというブランド名をつけました。1921年、堤商会は日魯漁業(現マルハニチロ)となり、堤は初代会長、平塚は初代社長に就任しています。
