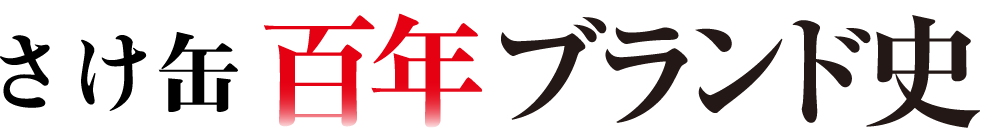
帆船宝寿丸の出航とともに幕を開けた北洋漁業。その3年後に生産された704函のさけ缶が、最初のさけ缶、「あけぼの さけ」となった。その歴史は、苦境のたびに再生をとげてきた日本のサケ・マス漁の歩みそのものと言える。百年以上続くブランドには、北洋の開拓以来、サケと共に生きた日本人の誇りと意地と情熱とが詰まっている。



平塚常次郎(25)が出会う
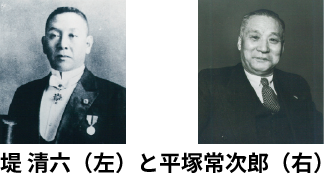




初めてのさけ缶「あけぼの さけ」誕生
ウスチ・カムチャッカ243号漁区に小規模缶詰工場が設営された。当時の缶詰はブリキ板を足踏み機で切断するなど、人力頼みだった。


赤白黄3色の商標を使用
日本初のサニタリー缶
ACC社から自動製缶機と缶詰機械1連を購入。オゼルナヤ工場において、日本初のサニタリー缶(衛生缶)の大量生産を実現。


初年度生産16,000函
缶詰が母船で生産されるようになる。1932年には70,000函を生産。カムチャッカを現地、函館を基地として、全国に商品を流通させていく。


5,603t出港
「サケで潰れるなら本望」
母船式操業の事業化には莫大な資金を要し、金融筋の大反対を受ける。しかし社内では「万一失敗しても、サケで生まれた会社が、サケで潰れるのは本望」との主張が大半を占めた。


小型缶の需要拡大
1960年の輸出向け1ポンド缶生産終了に伴い、1961年、小型缶需要拡大へ向け、F3号缶が木函96缶入りで生産開始。1962年には木函のF2号缶96缶入りが段ボール函48缶入りに切り替わる。


工船さけ・ます缶詰生産終了
200海里時代に入り、各国が資源の主権を唱え始める。母船式サケ・マス漁業は縮小。サケ・マス漁獲割当の激減と、冷凍品価格の堅調な推移から、工船によるさけ・ます缶詰の生産を断念。


T2号缶(ツナ2号)
それまでさけ缶の主流だったF2号缶が、原料の高騰からT2号缶に切り替わる。


最後の操業
最後の母船が……
喜山丸が最後の航海を終え、
サケ・マス漁業の歴史に
幕を下ろす。

喜山丸



EO缶あけぼの さけ


発売

復刻版あけぼの さけ


「あけぼの さけ」100周年

